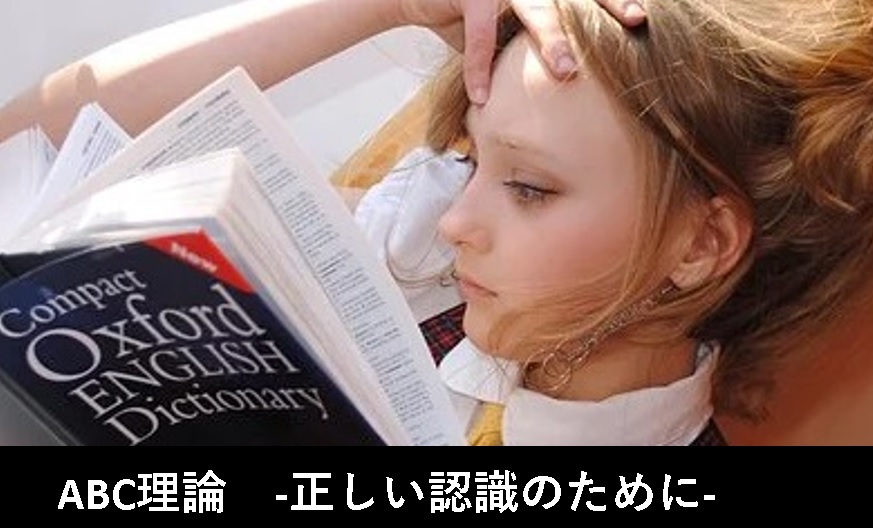
ABCDE理論(ABC理論)は受け取り方で解釈が異なるとする考えです。
ABCDE理論はA~Eの流れで物事を結論まで導くとする考え方です。
A=Activating event(出来事・環境)
B=Belief(認知・信念・思考)
C=Consequence(感情・感覚・行動・結果)
D=Dispute(反論・反発)
E=Effect(結論)
これらの頭文字をとってABCDE理論と呼ばれ、A→B→C→D→Eの順で考えると論理的な結果を得られやすいと考えられています。
一般的にはAの事象に対して、Cの感情が生まれると考えやすいですが、その前にBの認知が入ります。
そして、その認知が正しいのかを再検討して結論を導き出すのがABCDE理論です。
具体例
Aは実際に起こる事で人によってそれが変わる事はありません。
- 100万円あげると言われました。
これは事実のため、受け取る側の感情で内容が変わる事はありません。
Bは起こった事を認識しますが、認識の仕方は人によって異なります。
- 「素直に喜んでもらう」「本当にもらえるのだろうか?と疑問を持つ」「詐欺ではないのか?と疑う」
このように事実の認識は人の感情で異なります。
Cは認識した事に対して、どのような行動を取るかが人によって異なります。
- 100万円を受け取ったとします。
基本的に「100万円を受け取る」「100万円を受け取らない」に二択の行動となりますが、選択肢が複数になることもあります。
DではBの認識が正しいのかを確認します。
- Cで選択した100万円を受け取るという事が正しかったのかを確認します。
この際にBの認識がどのように作用したのかを考えます。
100万円を受け取りなにごともなく平和に過ごせたのならば受け取っておいて問題がなかったという認識が生まれます。
Eはこの行動を踏まえ新しい哲学が構成されます。
- Dの認識が生まれるとそれが実績として蓄積され、今後は無償でもらえるならもらいたいと思うようになる傾向が強いです。
ABCDE理論の特徴
ABCDE理論は「B」が与える影響がとても大きいと考えられています。
これは「B」の認識や認知の仕方は受け取る側の知識・経験・感情などの心理状態で異なった意味を持ってしまうためです。
例えば、友達に声をかけたけれども、反応してもらえなかったとします。
その場合「友達に無視された」「友達に聞こえなかった」のように異なる認識が生まれます。
ここで「友達に無視された」と考えてしまうと、嫌われているという発想が生まれてしまいます。
しかし、「友達に聞こえなかった」場合は嫌われているとは思いもしないはずです。
このように認識が異なるとその後の行動にも影響が大きくでます。
そのため、この「B」を見つめなおすプロセスの「D」はとても重要です。
このように認識を見つめなおす事の重要性は心理学では重要視されています。
そのため、ABCDE理論は論理療法の分野で有効と考えられています。
まとめ
ABC理論を用いて自問自答する事で冷静で合理的な判断ができるようになり論理的思考が身に付きます。
論理的に物事を考える事ができれば感情に流されない正確な認識をすることができるため、目の前の事象のみではなく、先をみた行動を取る事ができようになります。
このような差が将来的に大きな差へとつながっていきます。
特に成功者と呼ばれるような人はABC理論を知ってか知らずか実践している事が多いようです。
また、ABC理論で欠かせないのが問題定義です。
この問題定義には多面的な視点で物事を考える水平思考や批判的思考の能力が必要人なるため、ABC理論を反復して行う事でこれらの能力も高くなっていきます。
これらの能力が向上するとIQのみではなくEQも向上していきます。
備考
ABC理論はアルバート・エリスが提唱しました。
現在では医療分野でもABC理論が用いられ、論理療法(理性感情行動療法)などとして知られてます。
関連記事
論理的思考(ロジカルシンキング)
水平思考(ラテラルシンキング)
批判的思考(クリティカルシンキング)
IQ(アイキュー)
EQ(イーキュー)
論理療法(理性感情行動療法)






 鈴木 歩(すずき あゆむ)
鈴木 歩(すずき あゆむ)






