
浮きこぼれ(吹きこぼれ)とは
概要
浮きこぼれは能力が高すぎて周囲となじめない人を指す言葉です。
一般的には先天的な影響から生まれながらにして高い知能や感性を持っていたり、学習塾などで積極的に習い事を行い高いレベルの教育を受けた影響で後天的に優秀になる人のどちらか・またはその両方である事が多いです。
特に、日本の学校教育の現場では基本的に生まれた年代で区切り集団活動をしています。
高校や大学に通うためには入試を受けて学力が近くなる傾向がある事から能力差は軽減されやすいですが、小学校や中学校の多くは居住エリアによって通う学校が分かれているため「授業が簡単すぎる」という印象を受ける学生は珍しくなく、全体の15%程度は「授業を退屈」に感じているそうです。
※小学受験・中学受験などによって学力が近い同年代の子供がいる環境へ編入する方法もあります。
そして、その中には足並みをそろえた教育内容で指導するには無理がある程学習能力の差が顕著にでてしまう生徒もいます。
※学習レベルに差がありすぎる場合は教師に求められる能力も高くなりますが、教員の指導能力にも限界があるため目の届かない事も多いようです。
また問題は勉強だけではなく、IQ(アイキュー)が高い人と低い人では思考レベルが異なってしまうため、一般的にはIQ(アイキュー)が20~30違うと会話は成立しないと考えられています。
その影響から日常会話のレベルも異なってしまい周囲とのコミュニケーションに問題が発生してしまう事も珍しくはない現象のため育て方に悩んでしまう保護者も多いです。
※本人の意思次第ではあるもののフリースクールに通う事を選択する人もいます。
高すぎる能力の弊害
特にギフテッドやタレンテッドの様に基本的な特徴として「一般的な能力よりも高い水準の能力を身に着けている」生徒や、親が教育熱心で英才教育によって後天的に能力が高くなった人が公立の学校で授業を受けていると周囲の学習ペースに不満を抱く傾向が強いです。
※学習レベルが高い環境で育てたいと考える親も多く、小学校受験や中学受験をするケースもあります。
これは学校の教育方針が「誰一人取り残す事のない教育」を目指しているからです。
※この方針自体はとても素晴らしいと思いますが、全ての人に最適な教育をする事はとても困難なのが現実です。
しかし、実際問題として公立の小・中学校には発達障害と考えられている生徒が8.8%程度いると考えられている事から、学習ペースを「足並みが遅い生徒に合わせる事」に不満を抱えてしまう生徒がでるのは必然とも考えられます。
※文科省(文部科学省)で学習や対人関係の面で困難を抱える子の数を集計した調査結果では注意欠損・多動性障害(ADHD)など発達障害の疑い(知的発達の遅れは除外)のある児童生徒が8.8%在籍していると推定され、内訳として小学校で10.4%、中学校で5.6%、高等学校で2.2%になっていると推定されている事から、対策として少人数指導などの支援を充実させるとしています。
さらに学習指導要領の問題だけではなく、優秀過ぎる生徒は同級生との日常的な会話でも能力の差が現れてしまうため集団生活に苦手意識を持ち、中には同級生の理解力が足りない事が原因となり「いじめ」を受けて登校拒否になったり、才能の使い方を間違えて「学級崩壊」の原因を作る可能性もありますが、多くの場合は群れる事を嫌い一人でいるケースが多いようです。
※ドラマやアニメ・漫画のように文武両道で容姿にも恵まれているような人は、孤高の存在となり周囲から孤立してしまう可能性も高いですし「足手まといと関わりたくない」という意識から一人を好む事も多いです。
浮きこぼれの具体例
浮きこぼれは「同学年のレベルよりも高い能力」をもっている事が原因となり同級生と同じペースで過ごす事が難しいです。
そして、若年者の場合は精神的には幼いため理性に乏しい傾向があるので「思ったことが言動に現れやすい」のも同年代の周囲の子供と摩擦が生じて孤立してしまう原因となる事が多いです。
そのため、自身よりも年齢が上の会話のレベルが高い人と話す事が多くなる傾向があります。
そして、このような環境によって大人と会話する事が増えると悪循環に陥ってしまい同級生とはますます会話が嚙み合わなくなり孤立を加速させて周囲との溝を深めてしまう事もあります。
具体的には
大人が毎日のように公園の遊具や砂場で子供たちと一緒に混ざって遊ぶのが楽しいと思えるのかを想像するとイメージしやすいと思います。
稀に子供と一緒に遊んでいる優しい親御さんを目にする事もありますが、多くの大人は子供に合わせた水準でずっと遊ぶ事には苦労すると思います。
しかし、学校で浮きこぼれてしまう子供は知的能力だけでいうと「子供の中に大人が一人混ざっている」状態で常に過ごす事になってしまいます。
知的に優れているといっても人生経験も乏しく、精神的に幼いため「同学年」の人と会話が成立しない事は大きなストレスになります。
また、学生時代は基本的に能力の高い人が能力の低い人に足並みを揃える必要があるため、能力が高い人は一方的に苦労する事が多いです。
※生涯を通じて能力が高い人は能力の低い人に合わせる事になりますが「年齢」や「居住エリア」のように「能力」で区分されていない環境では特に負担が大きいです。
しかし、社会に出ると逆転して学生時代には足並みを合わせてもらっていた人は置いてけぼりになる事も珍しくはありません。
※職場などでは選考の段階で一定レベルの能力がないと入社できないため能力が同程度の同僚が多いです。
海外では能力が高い生徒を飛び級という形で先の学習へ進ませることで能力が高い生徒が不満を抱かないような仕組みとなっているところも多いですし、能力の高い生徒を集めた専用の教育機関もあります。
※日本では発達障害の児童は適切な環境で教育を受けられる環境が多いですが、浮きこぼれてしまう子供の受け入れ機関は不足していると言えます。
浮きこぼれの気持ち
浮きこぼれの気持ちを考えるのは自分よりも年齢が大幅に下の教育課程に混ざる事を想像していただければわかりやすいです。
具体的には
- 自分が小学生ならば幼稚園生と一緒に混ざるイメージ
- 自分が中学生ならば小学校低学年と一緒に混ざるイメージ
- 自分が社会人ならば中学生と一緒に混ざるイメージ
このような想像をしていただければわかりやすいと思います。
自分の学力よりも低い水準の授業を受けても時間を持て余してしまう事は容易に想像できると思います。
例えば、中学生レベルの学力があるのに教員の教える授業は小学生レベルで、学習内容はひらがなやカタカナの練習からはじまり、漢字の書き取りなどを勉強します。
そうなると授業は面白くないですし、周囲との能力差が大きいため会話も理解されない事が多いです。
このような状態になってしまうのは日本の教育制度が年齢で授業内容を統一しているためです。
一部の高知能者は一般庶民が話す内容を「一般庶民が馬や鹿が鳴いていると認識する程度」にしか思っていないのかもしれません。
もちろん、天才と呼ばれるような人の中には人間性も素晴らしく、尊敬できるような人もたくさんいますが、教育環境や家庭環境をはじめとする成長過程で精神的にどのように成長するのかは個人差が大きいようです。
まとめ
日本ではギフテッドやタレンテッドに対する認知が海外よりも遅れているため、対策も見過ごされてきました。
そのため、本来ならば「進むべき道をサポートしてあげる事で将来大きな成果を出せる能力」が埋もれてしまいやすい環境です。
社会人になる過程では多くの人は「授業を聞いていないのに勉強は人一倍できる生徒」を目にした事があると思います。
※同じ内容の教育を受けても学習能力の差による理解度の影響は大きいです。
そのような生徒の多くは能力に見合った授業が提供されていない可能性が高く、公立学校の水準で学習を行っていると時間を持て余してしまう事も珍しくありません。
中には、本来ならば伸びる才能が伸び悩んでしまい不登校や引きこもりとなり学校に居場所がなく周囲から浮いた存在となってしまう事も珍しくありません。
このような事が起こらないように日本でも積極的に才能を伸ばせる環境の整備が必要です。
知的に優れていても適切な学習環境を提供されていない子供は潜在的にたくさんいると思います。
特に、現状では富裕層の親のもとで十分な教育を受ける事ができる子供がいる一方で、貧困家庭には十分な教育を受けさせられる経済的な余裕がないケースも多いです。
このような事を少しでも減らすためには天才児に理解のある人が一人でも増える事が大切です。
備考
浮きこぼれは吹きこぼれともいわれ、落ちこぼれの対義語とされています。





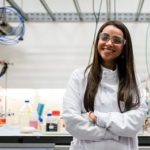
 鈴木 歩(すずき あゆむ)
鈴木 歩(すずき あゆむ)






