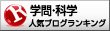臨界期仮説は一定の年齢までに学習を行わない場合、能力を取得するための難易度が上がるという仮説です。
臨界期仮設では言語取得の際の年齢が重要な要素となっている事が特に注目され定説とされているため、日本語教育検定試験にもでるほど有名な仮説になっています。
※臨界期仮説は保護された野生児や孤立児のように社会から離れて育った子供など、言語学習を受ける事が出来なかった子供を教育した成果から伺えるので賛同が多く支持されています。
臨界期として推測されている一定の年齢は12~16歳前後だと考えられる事が多く、これ以上年齢が上がると言語学習をはじめとした能力の取得に大きな壁があると想定されています。
※言語学習では基本的な単語を覚えたり文法を理解する事はできるようになることが多いですが、臨界期までに学習したかどうかで言語獲得能力が低下するため、発音や文法・構文などを取得(母国語並にできる)する難易度は非常に高くなる(取得できないわけではないが相当の努力が必要)と考えられています。
現代の日本では基本的に12~16歳前後(小学校を卒業する前後)まで母国語(第一言語)に触れずに育つことはないため、第二言語においての臨界期として考えられる事が多いです。
そのため、幼いうちから第二言語学び始めて12歳前後までに習得できた人はネイティブに近い発音ができる事が多いと考えられています。
言語の他にも視力・知力・愛着などにも臨界期があるのではないかと考えられています。
臨界期仮説が仮説である理由
臨界期仮説はその名の通り仮説で、実際に言語取得に与える影響が大きい年齢がいつまでで、それを過ぎるとどの程度の影響が与えられるのかは不明瞭な点が多いです。
これは個人の成長度合いや先天的な能力によっても個体差があるため分析を行う事が難しいという事もありますが、なによりも実際に実験を行う事は倫理的に難しいので明確な答えがでることなく議論が続いているのが現状です。
倫理的観点の具体例
幼少期の子供を言語に触れない環境で教育する事によって、その子供が実際に言語取得が困難になってしまった場合、その子供の将来の可能性を奪ってしまう事に繋がってしまうのが大きな問題となります。
また、言語に触れないという事は人との接触をしないように育てる必要があるため、成長過程でも人権を無視するような環境で育てる形になりやすく、多方面から倫理的な問題が出てくることが予想されます。
そして、このようにして得た実験結果もサンプル数が少なくてはけ結果としての信憑性が低いため、複数のサンプルが必要なので犠牲者も多くなる可能性が高いです。
臨界期仮説の根拠となっている事例
臨界期仮説の予測においては野生児が重要な例となっています。
野生児は幼少期になんらかの理由によって教育を受ける事ができなかった子供であるため、成長過程で言語取得ができない環境で育った後、保護されてから言語教育を行う事例も多くありますが十分な言語能力を身に着ける事ができない事が多いです。
野生児は現在でも発見される事がありますが、逸話が混じっている可能性も高いため、その全てを鵜呑みにすることはできません。
しかし、いくつかの事例では野生児の教育課程についてまとめられた文献もあります。
※狼に育てられたといわれている「アマラとカマラ」につていは作り話であったと考えられています。
過去に野生児として知られているのは
- アヴァロンの野生児(フランス)
1800年に推定12歳前後だとみられる少年が発見されました。
アヴァロンは幼いころから森の中で暮らし、野生児となっていました。
社会復帰を目指し教育をした結果、簡単な言語を理解する事はできましたが言語を取得する事はできませんでした。 - カスパー・ハウザー(ドイツ)
1828年に16歳と思われる少年が発見されました。
カスパーは孤児だと考えられていますが、長期にわたり閉じ込められていたため、言語を話す事はできませんでした。
教育を行い簡単な言語を理解できるようになり、過去を語り始めようとした21歳頃に何者かに殺害されてしまったため、カスパーの過去については未だに謎が多いです。 - 野生児ピーター(イギリス)
1725年に12歳前後と思われる少年が発見されました。
王宮に招かれ教育を受けましましたが、簡単な言語しか取得する事ができませんでした。
1728年からは農家の手伝いをしながら暮らし、推定70歳で亡くなりました。 - ジニー(ジェニー)・ワイリー
1957年に生まれ13歳までアメリカの自宅で監禁されて育ちました。
そのため保護された当時は年齢の割に体重も軽く、歩く事すら困難な状態でした。
保護されてからも一般的な生活を送る事が難しく居場所を転々と変えて過ごしています。
ここに挙げた事例はほんの数例ですが、このように保護された野生児の事例から臨界期は推測されています。
※野生児の言語取得に対する成果として、12~16歳前後で大きな差がみられています。
臨界期について
臨界期は言語取得に限った事ではなく、様々な能力の発達に影響を与えていると考えられています。
臨界期仮説は生理的早産(人の子供は未熟な状態で生まれているため環境適応能力が高いので大人になる過程で多くの可能性を秘めています)の延長で、未熟な状態で生まれる人の子供は12~16歳前後になるまでに多くの刺激を受ける事で様々な可能性を広げていくと考えられているため、幼少期には身近なこと(生活に必要な事を優先的に)に必要な能力を大人には難しいペースで獲得していきます。
そのため、日常的に触れる機会が多い生活環境はとても大切な要素だと考えられていますが、幼少期に文明社会で暮らす事の出来なかった野生児の中には、裸で冷たい外気の中に何時間いても平気だったり、暗闇の中でも色を見分ける事ができるなどの能力を獲得する例もあります。
野生児の事例と明社会で育った子供を比較すると、五感に関連した能力は特に異なった方向性になる事が多いです。
※ワーキングメモリ(地頭)には大きな差がない可能性があります。
野生児に多い特徴として、嗅覚や視覚や聴覚が良くなる事が多い反面、触覚や味覚が鈍感になる事が多いため、メリットだけではなくデメリットもあるためどちらが良いのかの判断は難しいです。
また、環境だけの問題ではなく個体の適正の問題もあるためそれぞれの能力の伸びしろの方向性を考慮した長所を伸ばす事で得意分野で目覚ましい活躍をする人も多いです。
一般的には先天的(遺伝的)な能力の影響で20~90%の差が生まれると考えられています。
※先天的な要素は、子供の成長ペースや特殊な技能を要する能力で教育やトレーニングによって補う事が困難な能力です。
また、成長過程の環境による影響が算数は55%・理科は45%程度だと言われているため、IQ(アイキュー)などの論理的思考(ロジカルシンキング)は後天的にある程度補う事ができる能力だと考えられています。
※遺伝や環境要因などの判断が難しいため、先天性・後天性の判断が難しいです。
先天的な適正がないと努力して上位になることはできてもトップになる事は難しいため、努力だけではギフテッドのような能力を身に着ける事は難しいです。
先天的な能力の例として、お酒が好きで毎日飲んでいても体質に合わない人と、お酒が好きではないけれど稀にしか飲まない人でも、後者の方が体質的にお酒に対する耐性が強い場合などは違いがわかりやすいと思います。
このような先天的な要因によって適正は変化しますが、日常生活に必要な基本的な能力は進化の過程で獲得してきた能力であるため遺伝的に大きな差はでにくいです。
しかし、例えば多くの人が言語習得をして文明社会に溶け込んでいる中、一切言語に触れずに大人になる場合は難易度が非常に高くなります。
このような例は非常にまれであるものの、幼少期に言語を習得できずに大人になってから学習を行うと単語などの基本的な事を覚える事はできても文法やイントネーションなどの習得には幼少期の何倍もの努力が必要になると考えられています。
これは成長過程による脳の生理学的な変化が影響(脳機能の左右分化が起こる時期が関係していると考えられている)しているという推測もあります。
また、臨界期仮説では言語獲得は第一言語(日本人の場合は母国語の日本語である事が多いです)だけではなく、第二言語の取得する年齢にも影響があると考えられています。
例えば、語彙能力は幼いうちに一定の水準の教育を受ける事ができない場合、その後の語彙能力に悪影響があるというものです。
また、家族全員で海外移住した場合、親には多少なりとも知識がある事が多いですが、全く知識のない子供の方が第二言語の習得が円滑にできる事も多いため、言語習得と年齢についての関連性があると考えられています。
外国語学習に関する適正調査によると16歳を境に第二言語の習得に差がみられました。
※12歳が臨界点だという意見もあるため、複数の推測がありますが16歳を過ぎても習得度が高い人も存在します。
言語学習には年齢以外の要素も関係している可能性があるため、臨界期仮説についての疑問は払拭されていません。
例えば、第二言語が日常的に交わされる環境に身を置き、積極的に言語習得を目指す事で10%以上がネイティブに近い文法や発音ができるとも考えられています。
まとめ
臨界期仮説では生活環境に適した能力の基礎は12~16歳前後までに決まると考えられているため、その後に環境が大きく変化して異なる能力が必要になっても取得するための難易度は非常に高くなってしまうと考えられています。
12歳前後まで全く言語に触れない状態の人が臨界期を過ぎてからの言語学習を行うと、簡単な単語などの理解はできるようになっても文法や構文などを身に着ける事がとても難しい事が知られているため、臨界期仮説には信憑性があると考えられています。
そのため、幼少期のうちに勉強を怠ると生涯を通して大きな悪影響を与えていると考えられています。
臨界期仮説で重要なのは臨界期以降は習得の難易度が上がると考えられているだけで、習得が不可能ではないという事です。
しかし、習得難易度が上がってしまうと多くの人が能力の取得を断念してしまう傾向があるので能力の適正を決める幼少期の環境はとても重要です。
また、言語取得のステップをいくつかに分類する考え方もあります。
- センシティブピリオド(敏感期)
この時期は能力の取得がスムーズにできる時期 - サイレントピリオド(沈黙期)
言語を話し始める前に発生をしない時期 - クリティカルピリオド(臨界期)
この時期を過ぎると学習難易度が非常に高くなる時期
このように言語取得を三つの時期に分類すると「言語能力が飛躍的に伸びる時期」から「言語を理解できるていてもそれに対しての返答に手間取る時期」を経て言語取得をしていきますが、その機会を逃してしまうと「言語学習に適していない時期」なってしまうと予想されています。
※返答に手間取る時期は、返答を考えてる間に話が流れてしまう事が多い時期です。
人は文明社会の一員として暮らすためには意思疎通が必要ですし、生活するためには多くの知識や経験が必要です。
しかし、完成された脳では伸びしろが少なく(適正が限られしまいます)なり知能の向上が難しくなるため、文明社会を学ぶのに適した脳の発育状態まで発達(この段階では身体機能が未完成の状態)した未完成の状態の脳(様々な可能性が残された状態)を持つものが生存者バイアスによって人口を増やしました。
そのため、現在の早い段階で生まれて少しでも早く能力を伸ばすスタイルが一番生存に適した進化であったはずです。
備考
言語学者及び神経内科医のエリック・ハインツ・レネバーグが提唱しました。
関連記事
アヴァロンの野生児
カスパー・ハウザー
ジニー(ジェニー)・ワイリー
生理的早産
IQ(アイキュー)
論理的思考(ロジカルシンキング)
ギフテッド
生存者バイアス






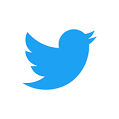 鈴木 歩(すずき あゆむ)
鈴木 歩(すずき あゆむ)