
収穫加速の法則とは
概要
収穫加速の法則は「知識や経験の蓄積によって技術的革新のスピードは指数関数的な伸びを見せる」という考えです。
アメリカの発明家であるレイ・カーツワイルは「一つの重要な発明が他の発明と結びつく事で新たな発明が生まれますが、発明が増えるほど結びつきのパターンも増えていくため次の重要な発明までの期間が短縮されていく」と提唱しました。
これは発明に限ったことではなく”既存の定義の証明”が進む事で革新的な方法が次々と立証されますし、技術が確立していく事でその技術を使った様々な「画期的な機械」「革新的なアイディア」が生まれ「秩序を保つための制度」が創成されるため新たな問題点やトラブルが更に発見され新しいイノーベーションが加速されていくと考えられています。
イメージとしては樹形図のように一つの点から複数の分岐が出現するように”なにかしらの進歩”があれば一定量の発見や成果は少なからず期待する事ができます。
このような事が繰り返されていく事で次の革新的な方法の発見までの時間が短縮され「一つの重要な発見が次の発見の足掛かり」となり次第に発展速度が早くなります。
このことから技術発展の際には直線的な右肩上がりのグラフではなく指数関数的な向上になると考えられています。
実際に私たちの技術力は数世紀の間に大幅な急成長を遂げたことから技術的特異点(シンギュラリテ)も近いと考えられています。
収穫加速の法則の具体例
私たちが学校で習う事は基本的に過去の偉人たちが残してくれた功績のたまものです。
特に理系分野では私たちが証明する事が難しいような理論を使った学習を行います。
例えば
理科の授業では多くの実験をテキストに記載されている結果を見ながら学習を進めていきます。
そのため例えば生物の分野で人体の構造を学習する際には実際に人を解剖して学習するという事はしません。
このように知識がない状態でも過去の資料を基に学ぶ事で学習時間を大幅に短縮し効率よく学習を行う事ができます。
また古典物理学(ニュートン力学のように視認できるような現象をメインに扱う物理学が代表的です)ならまだしも現代物理学(相対性理論や量子力学などが代表されるおおむね20世紀以降の物理学)のように観測するだけでも大変な事象の証明を基礎の基礎(実験器具の構造を理解や証明するところ)から始めていたら一生かけてそれだけで終わってしまいます。
そのため私たちが個人的に証明する事は現実的ではないものが多いです。
※実験器具だけでもかなり大がかりなものになったりその費用面でも個人で支払う金額として現実的な金額ではないと思います。
しかし、私たちの祖先によってこれらの多くの部分については既に証明がされているため既存の情報を基本として考える事ができます。
このように私たちは何世代にもよって研究された結果を知識として使う事ができるため技術革新は日々急成長を遂げています。
まとめ
私たちは祖先が残した過去の理論や法則などを知るだけで使う事ができます。
過去の偉人たちはその理論や法則などを証明するために膨大な時間を費やしましたがそのおかげで私たちはそれらの証明を省くことができます。
このように過去の実績を活かす事で新し革新的な技術の開発を行う際に大きく時間が短縮されるので私たちはコロンブスの卵のように今まで常識だと考えられていた事を覆すような革新的な技術を発想する必要があります。
しかし、現実では今まで常識だと考えられていた事が覆るというのは精神的に大きなハードルがあるためコペルニクス的転回(コペ転/パラダイムシフト)に代表されるように多くの大衆は発想は受け入れられずに障害となる事も多いです。
過去にも進み過ぎた研究は”周囲が理解できなかった”り”感情的な問題”によってその成果が受け入れられずにその分野での進展が遅れてしまった事が何度もありました。
※既得権益を得ているポジションの人がその地位や立場を保ちたいと妨害を企てるケースも多いようです。
これはギフテッドのような過ぎた能力を持つ人達が浮きこぼれ(吹きこぼれ)てしまうのと同じで社会全体にとって良い事ではありません。
このよな事を減らすためにもノブレス・オブリージュの考えが広く広まり優位な立場の人はその立場としての責任を果たすように努める必要がありますが、実際には自分の能力を過信してしまって他者の意見を聞き入れる事を忘れてしまう事が大半のようです。
このような”人の傲慢”がもたらす未来はグレートフィルター理論で問題となっていて「人類によって人類が滅ぼされてしまう自己破壊の未来」へとつながってしまうのかもしれません。




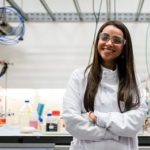

 鈴木 歩(すずき あゆむ)
鈴木 歩(すずき あゆむ)






