
ピーターの法則とは
概要
ピーターの法則は有能だったものは不適切な地位に昇進することで無能として留まってしまうという法則です。
基本的に能力主義の階層社会では能力に応じて昇進していきます。
しかし、昇進後の階層では能力の限界を迎えた後にさらに追加の能力を求められてしまうため、組織で求められる階級としての能力は不足してしまい周囲から「職位が正当ではない」「役立たず」などの悪評に繋がってしまうというメカニズムについて考えられた理論です。
これは能力の限界を超えた役職を与えられてしまう結果として各階層には「無能」と判断されるような人しか残らなくなっていまうという考えです。
この一番の原因は、昇進することで求められる能力が変化(現場で求められる能力と管理職として求められる能力は異なりますし、管理職として求められる能力と経営能力は異なります)し、その階層における必要な能力を満たせなくなる点でたとえ本来は優秀な人材でもその役職としては無能として扱われてしまいます。
※昇進するということは今までの職位での実績が認められた証明に近いですが、次の階級の能力が証明されているわけではありません。
つまり、個人的な能力は総合的には伸びているはずですが、求められる能力がそれを上回って上昇し続ける事でいずれ個人の能力以上の能力が求められるようになってしまいます。
※昇進後に必要な能力の難易度が上がるとは限りませんが、階層ごとに必要な能力が異なるため要求される能力が増加していきますし、全ての階層の能力に適性があるような人材は極稀なため、多くの人はいずれ能力の要求を満たせなくなってしまいます。
ピーターの法則の具体例
現場で有能だと思われている社員が管理職として昇進する場合
- 現場で求められる能力をAとします。
- 管理職として求められる能力をBとします。
現場でAの能力が高いと評価されて昇格しますが、昇進後に求められる能力は依然よりも多く(A・Bの能力が必要になります)なるため、無能(Bの能力が低い、または適性がない場合評価が悪くなってしまいます)となる可能性があります。
ここで有能(A・Bの能力が高いと評価される人)だと判断された場合、管理職から経営陣として昇進するとします。
- 管理職として求められる能力はBでした。
- 経営陣として必要な能力はCだとします。
昇格後に必要な能力は異なるため、ここでも無能(Cの能力が低い、または適性がない場合評価が悪くなってしまいます)となる可能性があります。
このように、昇進する事で求めらる能力が増加(例の場合はA・B・Cの能力が求められます)するため、それを満たせなければ無能として扱われてしまいそれ以上の昇進は望めなくなります。
そして、このような昇格人事が全ての人に適用される場合、各階層の全ての能力を満たせるような人材はほとんどいないため、多くの場合は各階層が無能(求められる能力を満たせない人材)な構成員で埋め尽くされてしまいます。
ハロー効果(後光効果/ハローエラー) による影響
現在のポジションで重要視される能力が高いとポジティブハロー効果の影響で他の能力も高いと周囲の人は錯覚してしまいます。
しかし、基本的に各階層で重要視される能力は異なるため、昇進後に重要視される能力が変わってしまいます。
そして、次のポジションで求められる能力が低い場合はネガティブハロー効果の影響により、他の能力も低いと周囲の方は錯覚します。
この結果、長所を活かしきれない事が影響して能力が過小評価されて周囲の人からは「無能」だと認識されてしまいます。
解決策
この問題を回避する方法は3つあります。
- 昇進させずに昇給を行う
- 現在の延長上の仕事を継続する事で専門性を磨きます。
- モチベーションの維持も期待できます。
- 昇進後に必要な能力を事前に習得させる
- 次の階層の能力を備えてから昇進させることで、昇進後も無能とはなりません。
- 次の階層の能力に欠ける方を事前に発見できます。
- 降格を行う
- 昇格させた後に能力が足りないと判断した場合は速やかに降格させます。
- この場合は周囲から批判されて本人のモチベーションが低下する可能性をなくす事ができますが、降格という事実によってモチベーションが大きく低下する可能性があります。
- 能力が不足している上司やリーダーがいると部下のモチベーションが低下するため、降格も一つの手ですが降格には大きなリスクが伴うためやりすぎには注意が必要です。
まとめ
ピーターの法則は現在能力のみを評価して昇格人事を行っていると、本人の適性とは異なった役職になってしまう危険性について考えられたものです。
人事評価はモチベーションに大きな影響を与える重要な要素なため正しい分析が行えずに本来の能力を発揮できないポジションに配属されてしまうと役職についた人もその周囲の人も大変な思いをしてしまうため人員配置によって生産性は大きく変わります。
「人事が変われば人が変わる、人が変われば組織が変わる」と言われるように目立たずとも影響力はとても大きいです。
しかし、人の能力を正しく見極める事はとても難しいです。
例えば、
同じ業務をしていてやる気がないA・Bさんがいるとします。
- Aさん
簡単すぎてやる気を出さなくても十分に成果を出せる - Bさん
難しすぎてやる気が出ないため全く成果がでない
このようなA・Bさんがいる場合、どちらに対しても「やる気がない」という評価をしている組織は多いです。
しかし、これは適性に対して求める程度のレベルが適正ではない事が影響していて正しい評価ができていない状況です。
本来ならばAさんにはより難易度が高い仕事を、Bさんにはより難易度が低い仕事を割り当てる必要があります。
そして、この二人に仕事を割り振っている上司はそのポジションに求められる能力が不足してしまっているため正しい業務の配分ができていない可能性が高いです。
このように、人員の配置が正しくできなければ様々なところに悪影響がでてしまいます。
備考
- ピーターの法則は1969年に南カリフォルニア大学教授の教育学者ローレンス・J・ピーターとレイモンド・ハルの共著「THE PETER PRINCIPLE」の中で提唱されました。
- 日本では1969年に「ピーターの法則―〈創造的〉無能のすすめ―」がダイヤモンド社から出版されました。





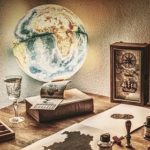
 鈴木 歩(すずき あゆむ)
鈴木 歩(すずき あゆむ)






