
センターピン理論とは
概要
センターピン理論は「影響力の大きいものに狙いを定めて効率よく成果をだす」という理論です。
基本的には物事には重要なポイントがあるためそれを見極め集中してアプローチする事で効率的に大きな成果が得られる傾向があります。
この様子がボーリングでの「センターピン(ヘッドピン)を捉える事でストライクを狙う」様子に例えられて提唱されているものです。
※ストライクは全部のピン(的)が倒れる状態です。
ボーリングの場合はセンターピンを倒さずにストライクを取る事は難しい一方で、センターピンを倒せれば後ろにあるピンも折り重なって倒れていくため多くのピンに影響を与える事ができるので仮にストライクにならずとも半分以上のピンが倒れる事が多いです。
※基本的にピンは後ろに倒れるため一番前のピンを倒すためには先頭のピンにボールを直接当てなければ全てのピンを倒す事は難しいです。
しかし、実際にはボーリングのようにセンターピン(要点)を目視できるわかりやすいものばかりではありません。
例えば会社などの組織で仕事をしていると「要領良くやれ」「本質を考えろ」などの注意を受けたり怒られてしまう人もいると思いますがそもそも”重要な項目を抑えられていない”傾向があるから注意されてしまう内容なので指示をする人が具体的になにをどうするのか説明しなければ改善する事は困難だと思います。
※上司の指示が支離滅裂なケースは案外多いですし部下の能力が高すぎて上司が理解できないという事例もあります。
このように実際には重要な人物やポイントに目印がついているわけではありませんし一見「狙いどころ」に思えるようなポイントでも案外無意味であるため見極める事が難しいです。
またプロジェクトなどでは重要な箇所が複数ある事も珍しくないため要点を抑えて効率よく段取りを組んでいく必要があります。
センターピン理論の具体例
会社などの組織においての重点を見極める事はとても難しいです。
例えば
会社で一番影響力の強い人は基本的には社長だと思いますがセンターピンは社長ではなく直属の上司かもしれません。
社長に直接意見を持っていってもなかなか反映されることは難しい反面、直属の上司が意見を反映させてくれる可能性もあります。
また、名ばかりの社長で実際には元社長である会長のワンマン経営であるというケースも珍しくはありません。
会社という限られた組織でも誰がキーマンなのか明確にわかりませんが、会社の外では誰と誰がつながっているのかもわからない状況で目的への影響が一番大きい人やポイントを見極めることはとても困難です。
企業ではこの効果を利用しようとインフルエンーサ(有名人等)による販売促進活動が繰り広げられています。
若者が真似したがる有名人(センターピン)に広告塔になってもらうことで、若者(後ろのピン)への販売が活性化されます。
※ステマ(ステルスマーケティング)という手法が広まり問題となり2023年10月1日から規制が開始されました。
本質を見極める方法
「要点をまとめて」や「ポイントを押さえて」と言われた事がある人も多いと思いますが物事の本質を捉える事は案外難しいです。
まず問題となるのは基礎知識で、スタートからゴールまでの全体像をつかめていなければ要点の把握は困難です。
※物事には順序があるため流れに逆らうとそれだけで難易度が上がってしまいます。
そして、流れの中には「絶対に遅れてはいけないポイント」や「外してしまうといけない内容」があります。
基本的にそれ以外の重要でない項目は除外されても遅れてもなんとかなる事で本質に付随しているオプションのような内容です。
よく例えられる言い回しとしては「骨を組む」状態から「肉付け」するイメージで、ここでいう「骨」が重要なポイントになります。
具体例としては
「幸せになりたい」という目標がある場合その過程では様々な欲望や理想があると思いますし、人によって理想像は大きく異なります。
ここでは「老後の安定的な暮らし」という目標を掲げて例をあげます。
近年発表された内容で「老後資金は夫婦で2,000万円必要」という試算が話題になりました。
基本的に2,000万円の資金を準備するためには20歳から60歳まで働く仮定の場合に年間50万円の貯金が必要になるため月々約42,000円の貯金が必要です。
※2000万円÷40年間÷12か月≒41,666円
これは夫婦の負担なので2人で約42,000円なら十分に確保できる水準に感じますが、実際には子育ての費用や近所付き合いや友人との交際費など諸々の費用が嵩んでいくと少し油断すると想定が崩れてしまう水準だと考えられます。
そのため、多くの人はそれだけ貯金できていないと思いますし全ての国民が毎月40,000円以上の貯金をするようになると日本の経済は鈍化して景気が低迷してしまうと思います。
収入が多くお金に困っていない人は多く貯金ができるかもしれませんが低所得者には厳しいのが現状です。
そんな中でも少ないお給料から上手に倹約してコツコツと貯金している人もいるので頭が下がります。
しかし、過度な節約は大きなストレスとなってしまいますし、極端な消費の削減や効率を軽視した方法はあまり得策ではないかもしれません。
例えば
- 近所のスーパーよりも1時間歩いたスーパーの方が10円安く売っているからそこまで買い物に行く。
- 光熱費の節約のためにトイレは近所の公園を使う。
このような行動によって得られる節約効果はとても少ない反面、多くの時間を使ってしまいます。
「健康のために少しでも運動した方が良い」などの考えがあれば完全には否定しませんが、他にも時間を使いたい事はいくらでもあるはずです。
近所のスーパーまで1時間の時間を使って10円節約するよりも、1時間働いた方が遥かに生産性は高いはずですし、トイレまで行く時間も同様に多くの時間を使っているのに効果は薄いです。
その時間を使って勉強したり、働いて収入を上げるなどした方がコスパ(コストパーフォーマンス)やタイパ(タイムパフォーマンス)に優れています。
このように「その活動によって得られる効果」と「他の方法によって得られる効果」を吟味してよりよい選択を行っていく事の積み重ねによって将来の状況は大きく異なっていきます。
また、近年話題に上がるようになった「FIRE(ファイア:Financial Independence, Retire Early)」も若者の間で人気ですが「やりたい事」があって仕事を早期リタイヤする人は少数で、多くの人は「仕事をしたくない」という理由が多いように見受けられますが実際のところはやりたいことがない状態で早期リタイヤしても再び仕事をする人が多いようです。
※基本的に稼ぐ能力が低い人は早期リタイアできずに「時間が足りない」傾向がある一方で、稼ぐ能力が高い人は早期リタイアしても「時間を持て余す」傾向が強いので「FIREして自由気ままに過ごす」には特殊な能力が必要なのかもしれません。
まとめ
センターピン理論では全体に影響があるポイントを抑えて効果的に物事を進めるのが重要だという考えです。
しかし、実際には要点を見定める事は難しくて多くの人が誤解してしまったり途中で目標が変わってしまう事が多いです。
※生存者バイアス(生存バイアス)のように根本的な認識を間違えてしまうと大きく認識が異なってしまう危険もあるので注意が必要です。
なにを目指すのかで要点は異なるので具体的に「〇をしなければいけない」という事は断定できませんが「必須事項」や「絶対条件」などの「本質」を見極める能力が必要不可欠になります。
※基本的な事は大切なため「基本」と言われているので案外答えは身近にある事も多いです。
そのため、要点を抑えるには経験や知識が必要になることが多く、それらを総合的に判断する能力(水平思考、批判的思考、論理的思考など)も必要になりますす。
その結果、目標から大きく外れる事は減少しますし、目標から逸れる可能性が出た時は違和感を感じるようになります。
それでも的に当たらない事はありますが、知識や経験がない時よりは格段に成果を残せるはずです。
俗にいう「要領がいい人」はこのような重点を絞ってアプローチする事が上手な人だと思います。



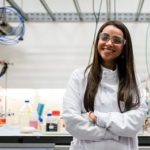


 鈴木 歩(すずき あゆむ)
鈴木 歩(すずき あゆむ)






